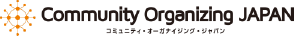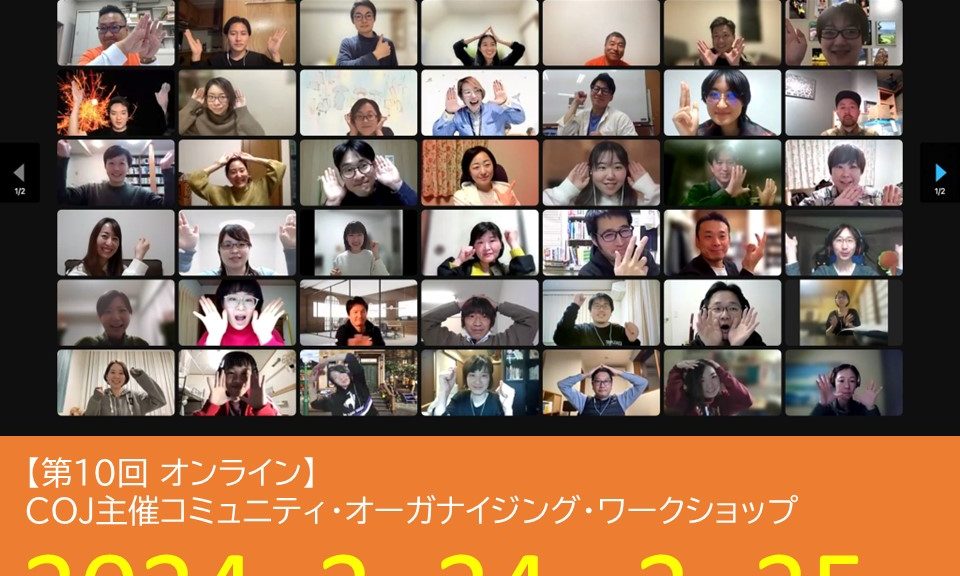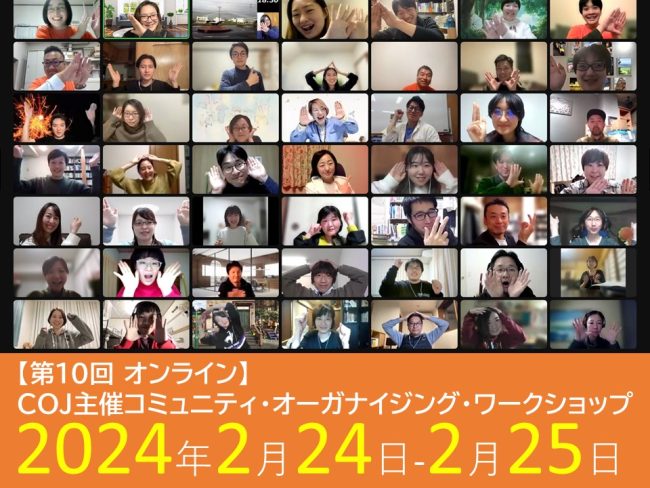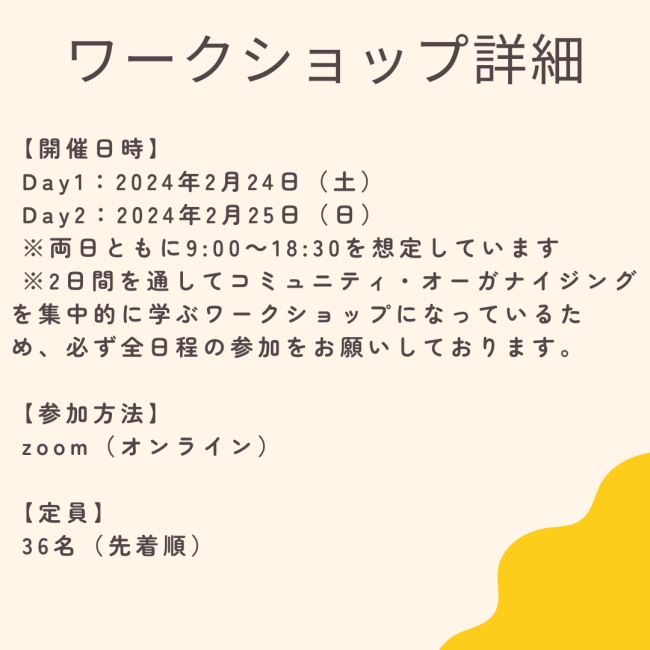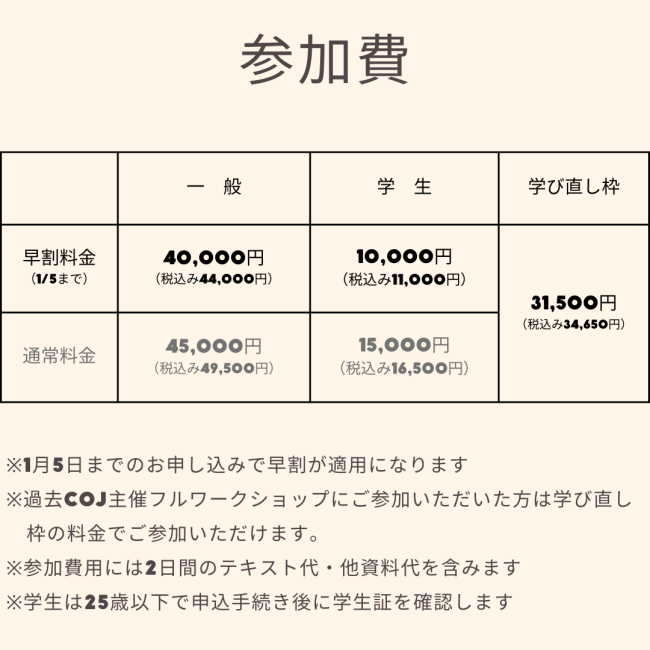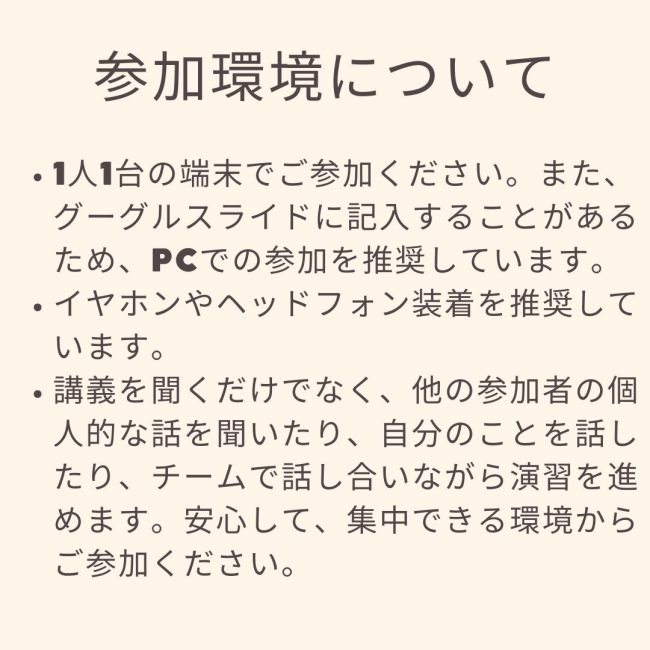2023年9月9日(土)、福島県福島市のチェンバ大町にて、「コミュニティ・オーガナイジング・”ミニ”ワークショップinふくしま」が開催されました。
今回の企画は、2019年2月に同会場で開催された2日間のワークショップに参加したメンバーが中心でした。ワークショップを経験後に、紆余曲折を経ながらも勉強会やお互いのコーチングなどを継続してきたメンバーです。続けてきた中で、「もっと多くの福島の人たちに、コミュニティ・オーガナイジングを知って欲しい」「もう一度、福島で学ぶ機会をつくりたいよね!」という思いから出発し、半年ほどかけて準備をすすめ実現しました。
コロナ禍を経て、久しぶりに対面式でおこなうワークショップに参加したのは23人。福島県内で市民活動に取り組む方、自治体職員、教育関係者など、幅広い分野の方たちがコミュニティ・オーガナイジングに関心を寄せて参加してくれました。(ちなみに、コーチ陣の多くは、県外から福島に想いを寄せ駆けつけてくれました。感謝!)
当日の朝は、会場が開くと同時に参加者が集まり、10分程度で受付が完了。学びに対する前のめりな気持ちが表れているようでした。
今回のワークショップの内容は、①コミュニティ・オーガナイジングとは?、②コーチング、③パブリック・ナラティブとは?/ストーリー・オブ・セルフ、④関係を通してパワーを構築する(関係構築)、⑤リーダーシップチームの構築。参加者は講義を聞き、4チームに分かれて演習にチャレンジしていきました。
朝の主催者あいさつを経て、チェックイン。はじめて顔を合わせる人たちも多くあり緊張した雰囲気がパッと明るくなりました。
講義は「導入:コミュニティ・オーガナイジングとは?」で歴史との関連や体系的にまとめられてきた流れを学び、「コーチング」の講義と演習へ。動画で悪い例、良い例のイメージをつくってグループで実践スタート。頭、心、手、5つのステップを意識してチャレンジした振り返りでは、「 課題が3つの視点のどこなのか、自分でもわからないので、コーチングで質問され、見えるようになった」との声も。

ストーリー・オブ・セルフでは、短時間でつくることに苦戦する参加者がいる一方、自身の体験を織り交ぜて、強い意志が伝わるセルフを披露してくれた方もいました。チャレンジした参加者からは「過去とのつながり、動いていることがわかった。つながったことで納得感を得られた。やりたいこと、やり始めていることに自分自身が信じて良いんだと思った」や、「この場はノームがあって、安心して自分のことを話せる。そして、強いストーリーは心に響きますね」という感想がありました。
朝から濃い講義とワークをこなし、遅い昼休憩。参加者同士の交流も賑やかにすすみました。
午後は「関係構築」の講義から。
午前中のセルフを元に、チーム内でペアをつくって共有する価値観、それぞれが持っている関心と資源を探るワークをおこないました。関係構築をすることで「自分にどんな資源があるかわからないと思ったが、ペアの人が気づかせてくれた」や「ワクワクした」と、可能性が広がる感覚を持つことができたようです。
その後、今回の最後の単元となる「チーム構築」へ。限られた時間の中で、チームの共有目的、チーム名、チャントを決めていきます。ここまで来るとチーム内のテンションもあがり、活発な意見が出されてくるのが印象的でした。時間をめいいっぱい使って、チーム名、チャントを決めて発表です。
1日を共にしたチームの発表は、どれも思いや資源が出ている特徴あるプレゼンテーションでした。

最後の振り返りは、全員で円をつくって一人ひとり「気づきと学び」を発表しました。
- 「午前中の時から時間が経つのが早い。理解できないこともいっぱいあったし理解できてもしきれない。こういう世界に触れられた経験は大きい。この経験を無駄にしたくない。なんかしていきたい」
- 「チームが上手く機能しないのは当事者とやってないからだと気がついた。組織にどうやって落とし込むか。今やっていることをストーリに落とし込みたい」
- 「学校に勤めていると視野が狭くなってしまうので、視野を広げるため参加した。ヒントになることがいっぱいあった。現場で活かしたい。硬い椅子に5時間座る子どもたちを尊敬する一日だった」などなど。

4年半ぶりに福島で開くことができたコミュニティ・オーガナイジングのリアルな学びの場でした。ワークショップ後、企画をした福島メンバーと今回の参加者による月イチ勉強会がスタートしています。今後の展開にも期待!?
(コーチ:小抜勝洋)