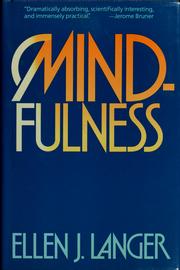勇気を持って共に走る仲間が集う!
勇気を持って共に走る仲間が集う!
特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパンでは、2014年の設立以来、ワークショップを数多くの開催し、全国各地・各分野で、受講者の輪と実践の輪が広がっています。次へのアクションを生み出す実践応援の輪をみなさんと広げていく場を開こうと、2016年3月27日に『オーガナイザー祭』を開催することに致しました。ワークショップ参加者の方をはじめ、コミュニティ・オーガナイジングの活動にご興味がある方は、ぜひご参加ください。
《こんな方にオススメです》
・COの手法を実践に活かすイメージを掴みたい
・多様な実践事例から学びと気付きを得たい
・共通の価値観、関心を持って活動している人と関わるきっかけがつくりたい
・自分の活動の可能性を広げたい
・実践を相互応援するコミュニティを自分の地域で作りたい
・子育て・教育、介護・福祉、労働などテーマに特化して実践を相互応援できるコミュニティを作りたい
・COワークショップを自分のコミュニティで開催したい
《オーガナイザー祭の内容》
【① オリエンテーション】
世界的なコミュニティ・オーガナイジングの動きとコミュニティ・オーガナイジング・ジャパンの活動報告を、特定非営利活動法人コミュニティ・オガナイジング・ジャパン代表理事 鎌田華乃子が行います。
代表理事 鎌田華乃子
【オーガナイザーセッション】
『オーガナイザー祭』では、オーガナイザー一人ひとりが得られた実践からの学びや気付きを共有し、交流を深め、オーガナイザー同士が継続的に実践を応援できるような契機にして行きたいと思っております。
(第1部)
オーガナイザーセッション第1部では、ご自身の取り組まれている活動にコミュニティ・オーガナイジングの手法を取り入れられた『まんまるママ岩手』佐藤美代子さん、「想い」をカタチにゼロからオーガナイジングプロジェクトを始められた『ちゃぶ台返し女子アクション』大澤祥子さん、ご自身が活動されている組織の中でオーガナイジングプロジェクトをされている『生活クラブ風の村』の島田朋子さん、3名によるコミュニティ・オーガナイジング実践事例発表を行います。本セッションのコーディネーターは副代表理事 室田信一(首都大学東京都市教養学部准教授)が行います。

コーディネータ:室田信一
(第2部)
テーマごと、地域ごとのオーガナイザーブースに分かれて、オーガナイザーと参加者がインタラクティブに実践活動の共有をする時間を設けております。
『特定非営利活動法人 いわて連携復興センター』 葛巻徹さん
『LGBT成人式』 松川莉奈さん
『おせっかいバトン』 本多智子さん
『プレカリアートユニオン』 清水直子さん
『Clinked』 依田純子さん&大野まきさん
『特定非営利活動法人 ソルト・パヤタス』 井上広之さん
『KAKE COMI』 鴻巣麻里香さん
『夢追塾』 園田恵さん
ほか
※「登壇オーガナイザー」情報は順次更新致します。
【全員参加型ワークショップ(予定)】
『市民一人ひとりが、自らの価値観にもとづいて能力を発揮し、そのパワーを結集することで困難や課題が解決され、さらにその挑戦が応援される社会』(COJビジョン)の実現へ。オーガナイザー祭終盤のワークショップでは、例えば、「実践を相互応援するコミュニティを自分の地域で作りたい」「子育て・教育、介護・福祉、労働などテーマに特化して実践を相互応援できるコミュニティを作りたい」「コミュニティ・オーガナイジングのワークショップを自分のコミュニティで開催したい」など、参加者の方から出していただいた話したいテーマを題材に、興味・関心を持った人同士で輪を作り、具体的なアクションに向けたキッカケ作りを行います。
《イベント概要》
■日時
2016年3月27日(日)
開場 12時30分
開始 13時
終了18時
※途中入退場可
■開催場所
日本財団ビル
〒107−8404 東京都港区赤坂1丁目2番2号日本財団ビル
【最寄駅】
東京メトロ 銀座線「虎ノ門駅」 徒歩5分
東京メトロ 南北線・銀座線「溜池山王駅」 徒歩5分
東京メトロ 丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前駅」 徒歩5分
【JR東京駅から】
東京メトロ 丸の内線に乗換え→「国会議事堂前駅」(駅間所要時間 7分)
■ 対象者
コミュニティ・オーガナイジングワークショップ参加者・参加予定者
社会問題の解決に関心のある方、草の根活動を広げたい方
※NPOリーダー、市民活動のリーダー、企業のリーダー(企業規模や役職に関わらず)、行政担当者など
■参加費
一般 2000円
学生 1000円
■申込み・支払いサイト
■問合せ・連絡先
特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン
〒105-0004 東京都港区新橋4-24-10 アソルティ新橋502
E-mail: info [at] communityorganizing.jp
担当:コーディネーター 杉本篤彦
■主催
特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン
<コミュニティ・オーガナイジングとは>
市民1人ひとりの力は小さいが、沢山の力が合わさることで強い力が生まれ、問題解決に立ち向かえるようになる。そのために市民1人ひとりが主体性を伸ばし、共有する価値観のもとに協力し、共に学び成長しながら、問題解決を目指すことをコミュニティ・オーガナイジングといいます。
■参考情報
コミュニティ・オーガナイジングやCOJについてメディアで掲載された情報
● “物語”の力が社会を変える|NHK クローズアップ現代
● 「コミュニティ・オーガナイジング」を通じて、一人ひとりが社会変革の主役となるには ~マーシャル・ガンツ博士 特別講義|現代ビジネス
● 「日本人に眠る能力を引き出したい」オバマ氏を大統領にした「コミュニティオーガナイジング」を広める鎌田華乃子さんに聞く「未来のつくりかた」|ハフィントンポスト
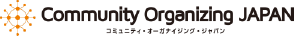





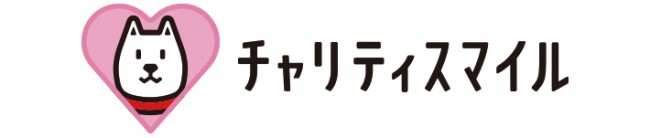


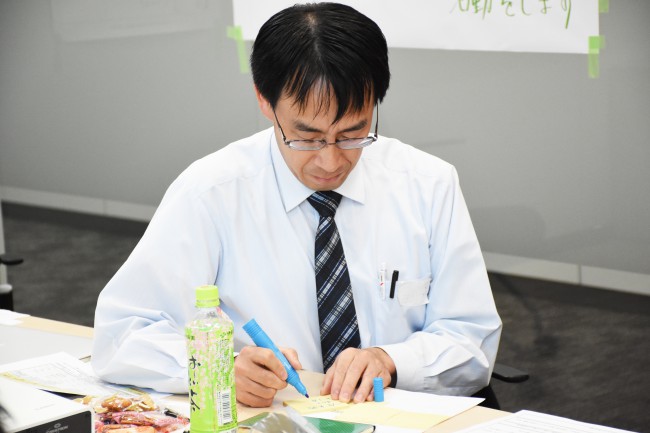



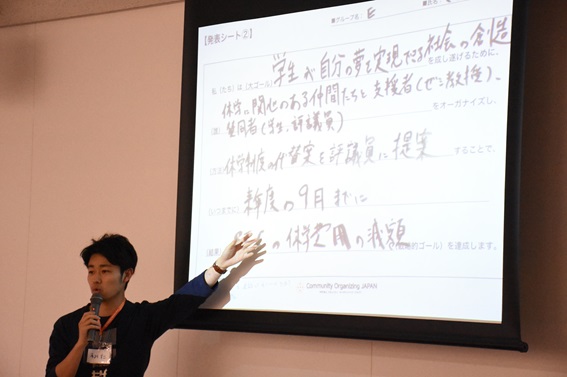


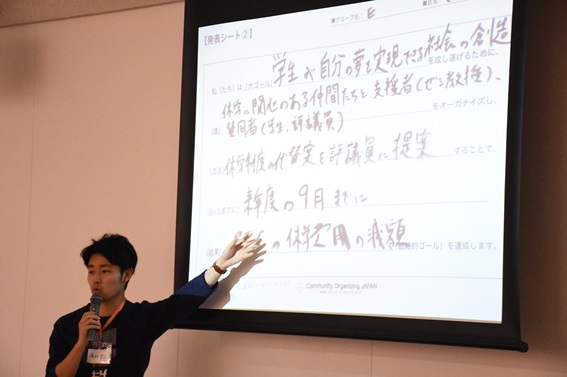







 勇気を持って共に走る仲間が集う!
勇気を持って共に走る仲間が集う!

 コーディネータ:室田信一
コーディネータ:室田信一