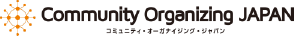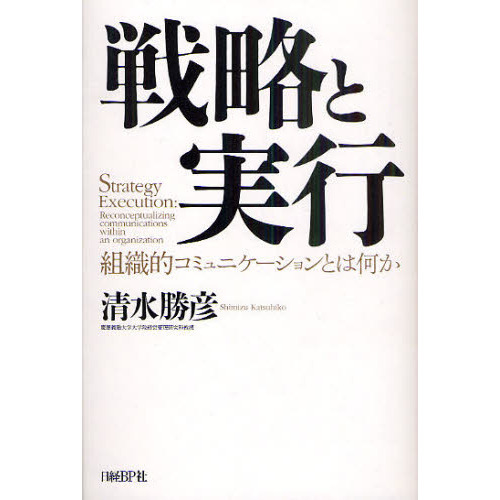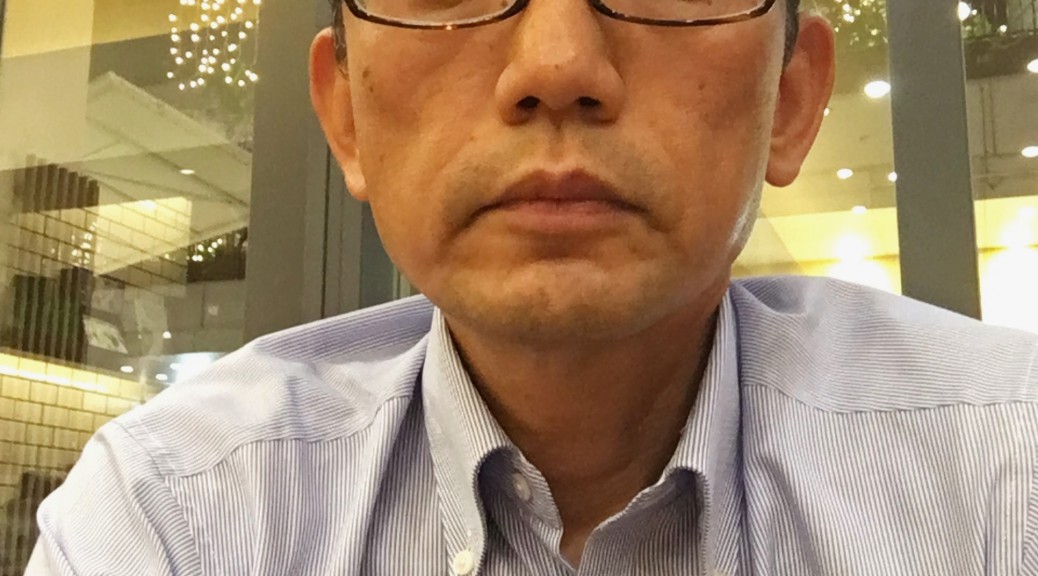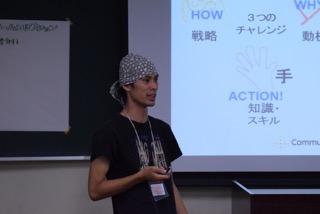※このコーナーでは、ワークショップを受講頂いた方、
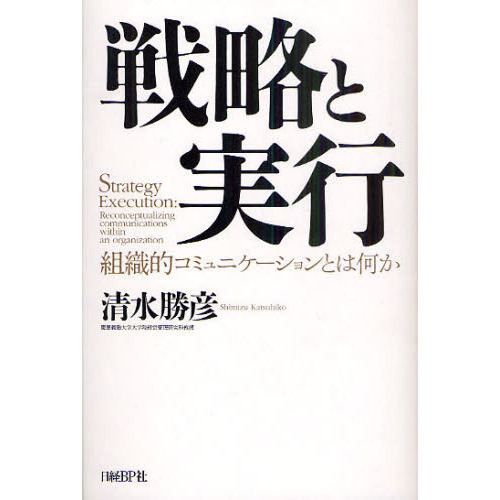
本書はMBAの先生が書いたバリバリの「ビジネス書」ではありますが、COJのWSを受けた人にはとても共感でき勉強になる内容だと思い、今回取り上げさせていただきました。
全編に渡って本当に刺激的なのですが、私は何よりも本書の白眉は副題にある「組織的コミュニケーションとは何か」について書かれた第3部にあると勝手に思っています。
どれだけ素晴らしい戦略を立てても、それが絵に描いた餅になっていては意味はなく、それをどのように実行するか。そのためにはコミュニケーションが大切である、というと一見なんの変哲もない内容に感じられるかもしれません。しかし、多くの人が大切で当たり前だと思っていることに盲点があることは、みなさんなんとかなく思いたるのではないでしょうか。
著者は「コミュニケーションの目的」を以下のように定義しています(P150)。
ーーーー
1.価値観や考え方が同じである人同士の間では、その合意内容についてよく確認する
2.対立する人たちの間ではお互いの価値観がどういうものかを知り、なぜ対立するのか、どこが対立しているのかをよく知る
3.そして価値観が同じでも微妙にある「違い」に気づき、また対立してもそこにある「共通点」を見つける
ーーーー
コミュニケーションの本質が、単にしっかりと会話をするなどとは次元の違うものであることがここからもうかがい知れます。また著者が「価値観」や「感情」というものをとても大切に扱っている点にも親近感を持ちます。
例えば
「組織におけるコミュニケーションとは単に論的なメッセージを伝えることだけではなく、感情、気持ち、あるいは人間性までを伝え、共有、共感を作り出す力なのです」(P174)
といったあたりは、思わずパブリック・ナラティブを連想する方も多いのではないでしょうか。
私が本書を推薦するのも、新しい情報や知見が披露されている訳ではなく、いわれてみれば当たり前のことですが、読んでいると「うん、うん、確かにそうだ」と自身の実体験なんども頷いてしまうことの連続であり、それがまさに最初にWSを受けた時の感覚となんとなく似ているからです。
COJのWSでも、内容的な目新しさというよりも、当たり前のことを妥協なくなく徹底して、ゴールの達成を目指すということを伝えています。私も含めて、人間どうしても易きに流れてしまうものだと思います。それを乗り越えるための知恵が満載の本書、是非一読してみてください。
最後に
「コミュニケーションとは、異なったバックグランド、考え方、そして感情を持った個人が、組織の一員としての自分のアイデンティティを知り、自分の意思を場合によっては曲げながら共同作業を行い(前向きの妥協)、個人の力を組織の力に高めるための、効率の悪いしかしおそらく唯一の方法なのです。」(P318)
と書かれています。
社会課題の解決には抜け道や必殺技はなく、一歩一歩着実に進めるしかないのは自明のことのように思われます。しかしどうしても弱さから「易きに流れて」しまうのもよくある話。そんな時に常に手元において襟を正しくなるのがこの本です。