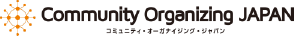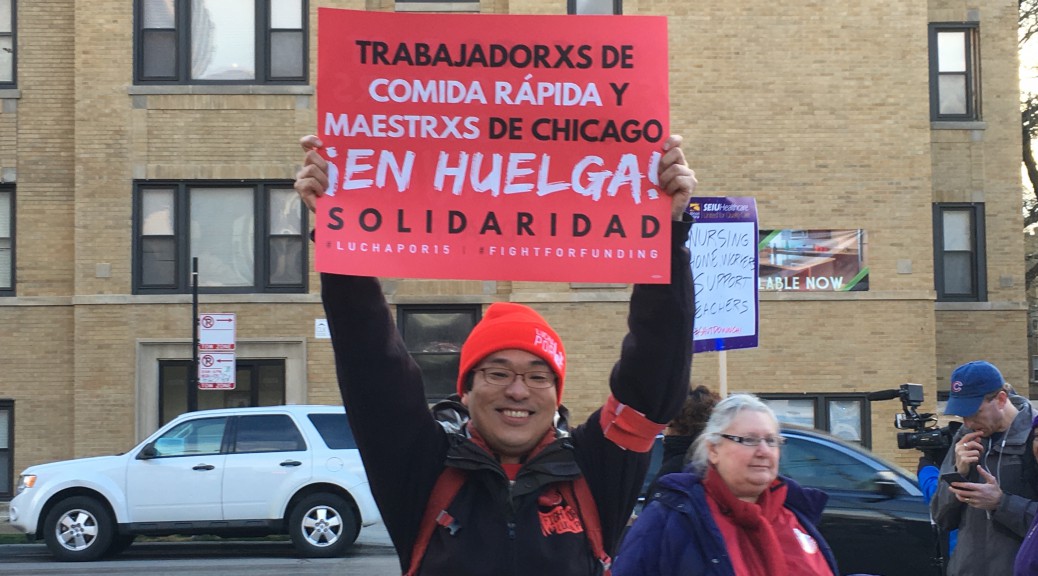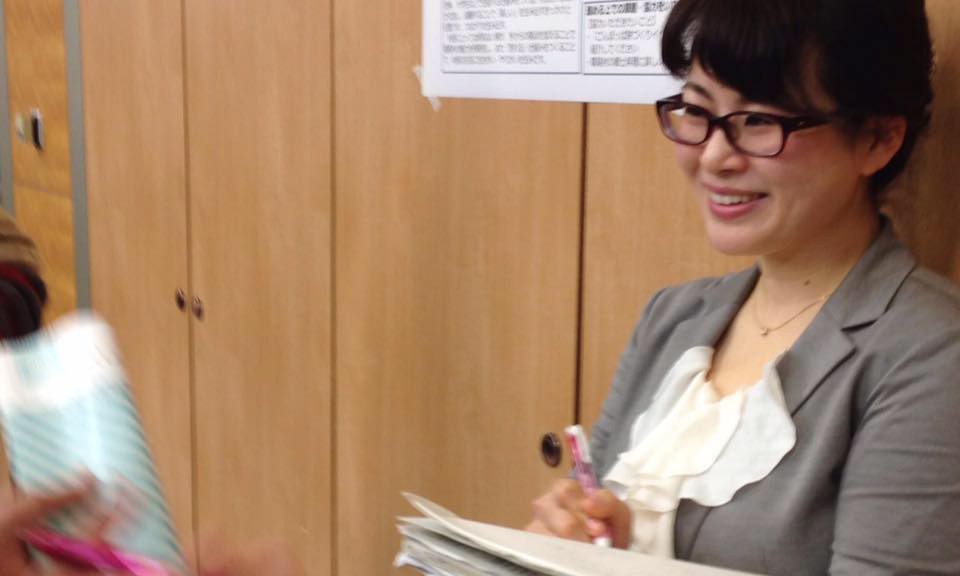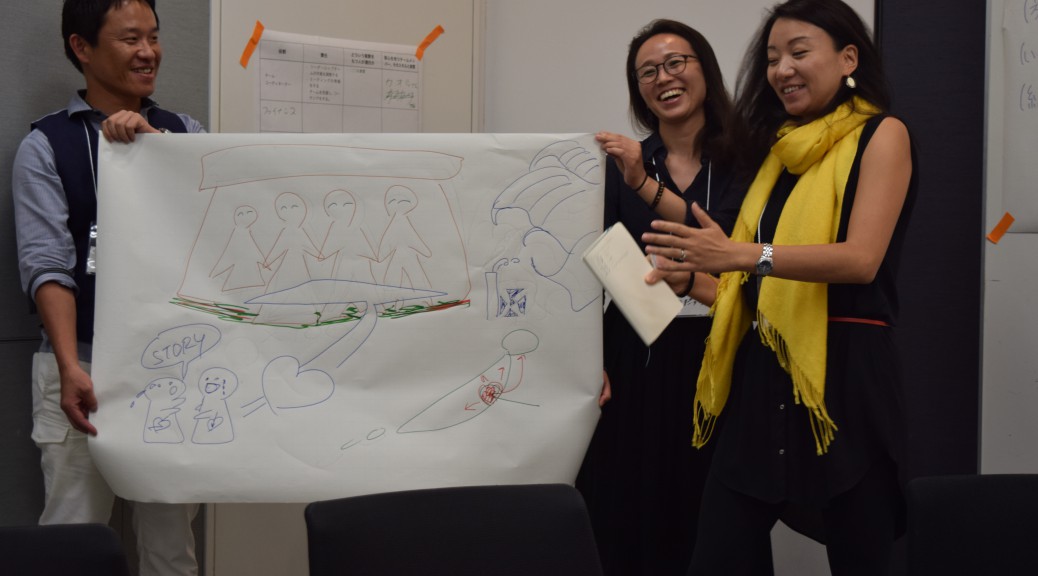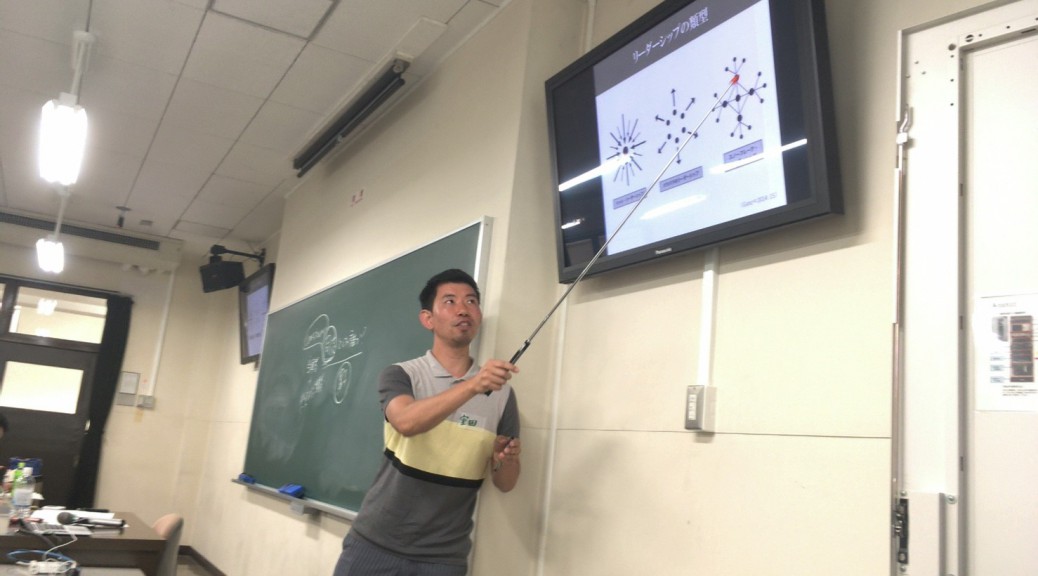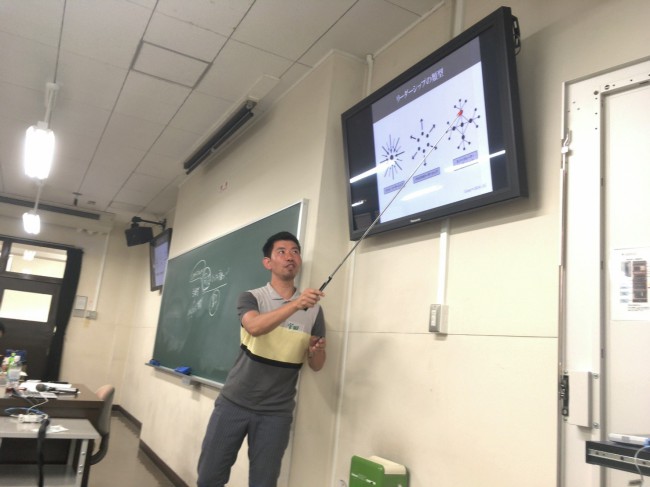私達、コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン(以下
(参考)2014年1月7日NHKクローズアップ現代【
http://www.nhk.or.jp/
これまでCOJでは中部地方でコミュニティ・オーガナ
前半代表の鎌田より『コミュニティ・オーガナイジング
対象は下記のような方々にご参加いただければと思ってお
●市民一人ひとりが、自らの価値観にもとづいて能力を発
●これから活動を始めるために、自分の価値観を伝え、一
●すでに活動しているチーム内で、チームメンバーに共通
今回をキックオフとし、本格的に中部地方で学びのコミュ
<日程>
2016年11月19日(土)13時〰17時30分(開
<会場>
名城大学名古屋ドーム前キャンパス 社会連携ゾーンsh
〒461-8534 名古屋市東区矢田南4-102-9
TEL:052-832-1151(代)
JR中央本線・名鉄瀬戸線「大曽根」駅下車 徒歩約10分。
地下鉄名城線 「ナゴヤドーム前矢田」駅下車 徒歩約3分。
shake:http://www.meijo-u.ac.jp/
地図:http://www.meijo-u.ac.jp/
<プログラム>
12:30 開場
13:00 開会・挨拶
13:10 講義1『変革を創るコミュニティ・オーガナイジング』
13:30 講義2『共感を生むストーリー 私の物語の伝え方』
14:15 演習1『ストーリーオブセルフ』
14:45 振り返り
14:55 休憩
15:00 講義3『価値観を共有する関係構築』
15:25 演習2『関係構築』
16:05 振り返り
16:15 休憩
16:20 パネルディスカッション
NPOリーダー、学生団体リーダー、企業人事担当
17:20 締めの挨拶
17:40 懇親会
<講師>
鎌田華乃子
特定非営利活動法人 コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン代表理事
横浜生まれ。11年間の会社員生活の中で人々の生活を良
<定員>
60名
<参加費>
シンポジウム参加費:一般(早割)2000円、一般30
懇親会参加費:3500円
<申込フォーム>
http://ur2.link/yNF2
<協力>
名城大学 社会連携ゾーンshake
<問い合わせ先>
特定非営利活動法人コミュニティ・オーガナイジング・ジ
〒105‐0004 東京都港区新橋4-24-10 アソルティ新橋 502
E-mail:info@communityorgan
担当:池本