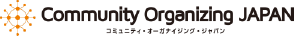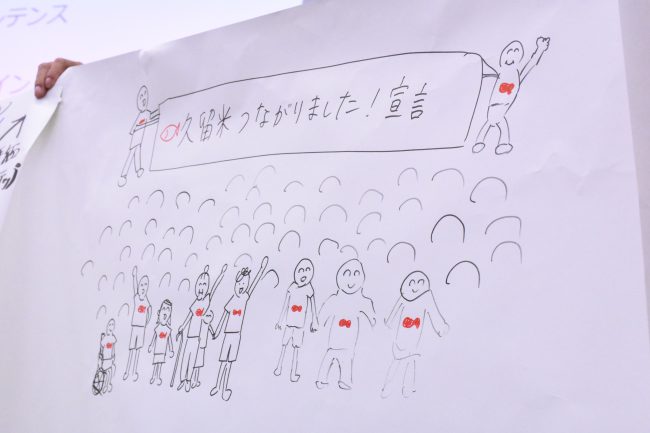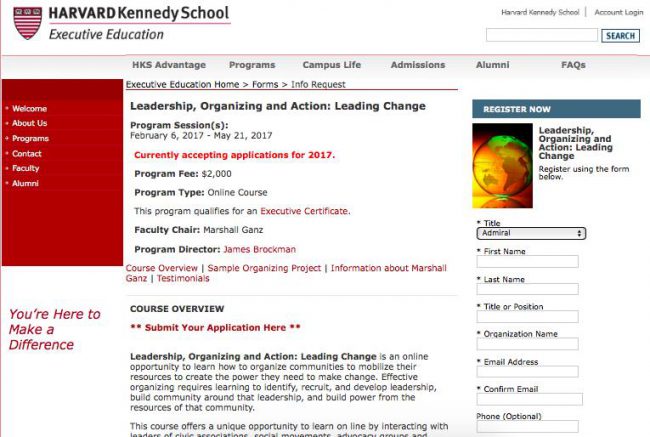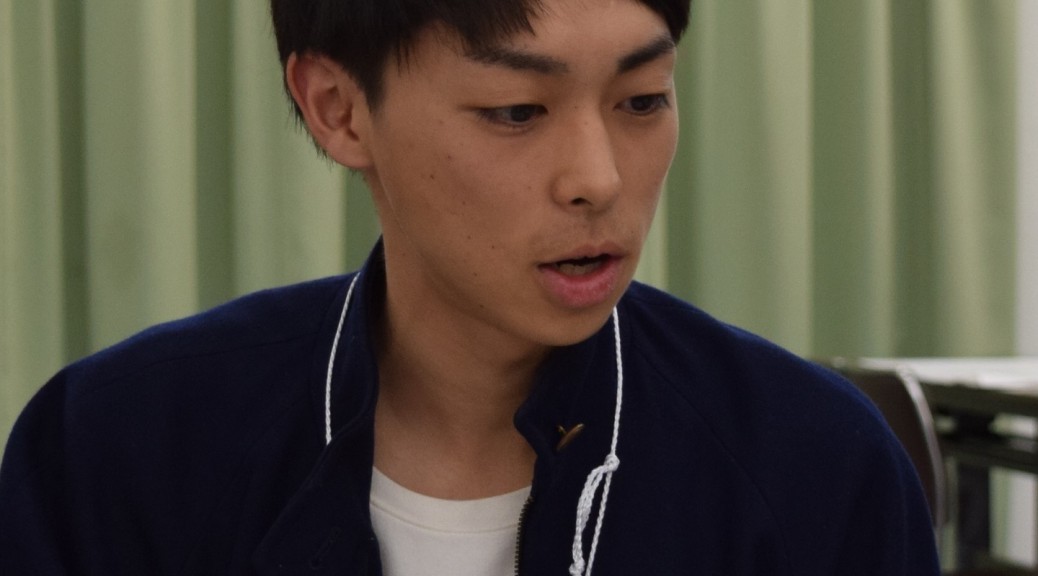2017年1月15日(日)、徳島市内のときわプラザ研修室1にて、「コミュニティ・オーガナイジング・ワークショップ」《パブリック・ナラティヴ編》を開催しました。主催は、地域の未来づくりに向けたワークショップデザインやファシリテーションを専門に行う一般社団法人しこくソーシャルデザインラボが行いました。また、徳島県福祉基金からの助成をいただいての開催でした。
 各地から 27名が参加。四国での初めての開催でしたが、地元の徳島県はじめ香川県/高知県/岡山県/兵庫県/京都府/静岡県と広範囲から参加いただきました。男性11名、女性16名、20代~40代が全体の85%を占め属性も社会人、主婦、NPO関係者、学生と様々でした。地域おこし協力隊や女性のキャリア支援NPO、労働組合、市役所職員など多彩なバックグラウンドを持つ参加者が集まりました。
各地から 27名が参加。四国での初めての開催でしたが、地元の徳島県はじめ香川県/高知県/岡山県/兵庫県/京都府/静岡県と広範囲から参加いただきました。男性11名、女性16名、20代~40代が全体の85%を占め属性も社会人、主婦、NPO関係者、学生と様々でした。地域おこし協力隊や女性のキャリア支援NPO、労働組合、市役所職員など多彩なバックグラウンドを持つ参加者が集まりました。

今回は、コミュニティ・オーガナイジング・ワークショップの中で、パブリック・ナラティヴに焦点を絞っての1日研修でした。参加者からは「ワークショップでは、筋トレのように短いエクササイズを繰り返し体と脳に刻み込ませたという印象。」「物事を伝えるための考え方や、思考の癖のようなものを理解できた。」「セミナーを受けてすぐに、SNSで自分のストーリーをシェアした時に驚くほど反響があり、活動を持続していく自信にもつながった。」「タイムスケジュールの管理など細部まで自主性と効率を重視した運び方がとても勉強になった。」「上手になるテクニックやノウハウではなく、企画全体に必要かつ重要なピースとしてのスピーチ構成を学ぶことができた。」といった感想が後日寄せられました。
 私自身の感想としては「社会変革の源泉は極めて個人的な経験やストーリーの中にある」ということが掴めたことが、何より収穫でした。私は現在、今回の主催団体である一般社団法人しこくソーシャルデザインラボの代表理事を務めるいっぽうで、普段は京都市内の同志社大学にて、教員として社会人向けの大学院でソーシャルイノベーションをテーマにした研究や教育を行っています。ソーシャルイノベーション、というのは今ある社会課題が生まれないシステムへと変革することを指すわけですが、確かにそれには行政や企業など既存の権力構造の変革が必要です。
私自身の感想としては「社会変革の源泉は極めて個人的な経験やストーリーの中にある」ということが掴めたことが、何より収穫でした。私は現在、今回の主催団体である一般社団法人しこくソーシャルデザインラボの代表理事を務めるいっぽうで、普段は京都市内の同志社大学にて、教員として社会人向けの大学院でソーシャルイノベーションをテーマにした研究や教育を行っています。ソーシャルイノベーション、というのは今ある社会課題が生まれないシステムへと変革することを指すわけですが、確かにそれには行政や企業など既存の権力構造の変革が必要です。
しかし、社会課題は常に個人の人生の課題として表れ、その集積が社会全体の課題となるのです。その課題を個人の問題として片付けてるうちは、システムの変革は起こりません。その個人が声を挙げ、周りの共感を集め、具体的な行動を起こすことにより初めて社会は変わっていきます。ですので、ソーシャルイノベーションの源泉は常に個人のストーリーにあることを、私自身今回のワークショップを通してはっきり学ぶことができたのでした。

そして、今後も大学の教育や地域での活動を通して、その個人の暮らしに具体的に表れている課題に焦点を当て、同時にそれを解決し乗り越えようとする人間の力と、それに共感・連帯して共に変わっていこうとするコミュニティの力、つながりから生まれるリーダーシップというものに常に目を開き、それを強め支援する仕事をやっていこう、と改めて強く感じることができました。
その意味で、今回は自分自身の人生の指針と仕事のありかたに、大きく影響を与えるものでした。講師として来ていただいた古くからの友人の鎌田華乃子さんはじめ、各地から集まっていただいたコーチのみなさん、そして参加者のみなさんにこころより感謝いたします。ありがとうございました。
文責:佐野淳也(一般社団法人しこくソーシャルデザインラボ 代表理事)