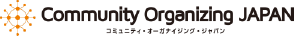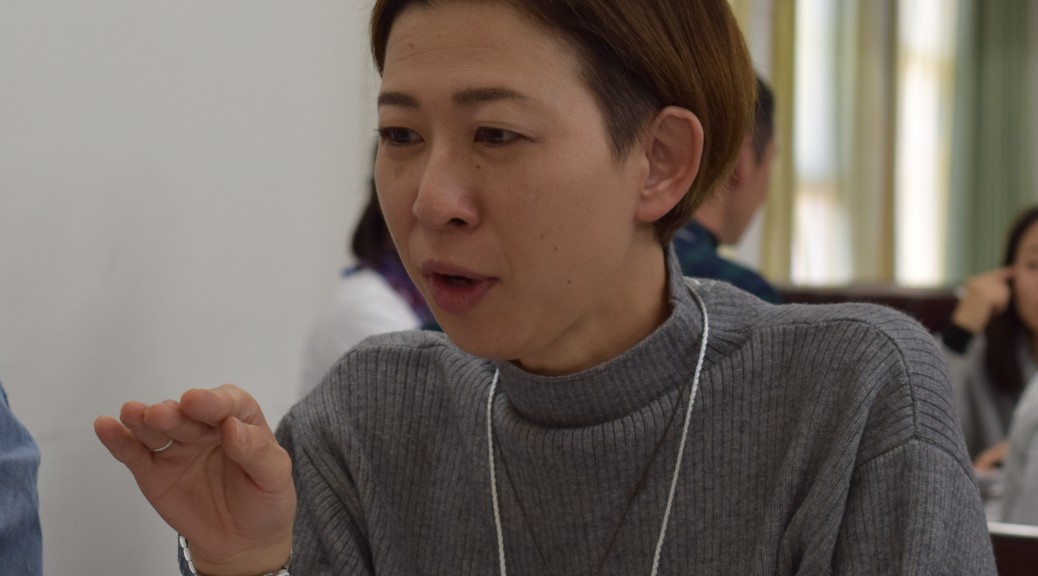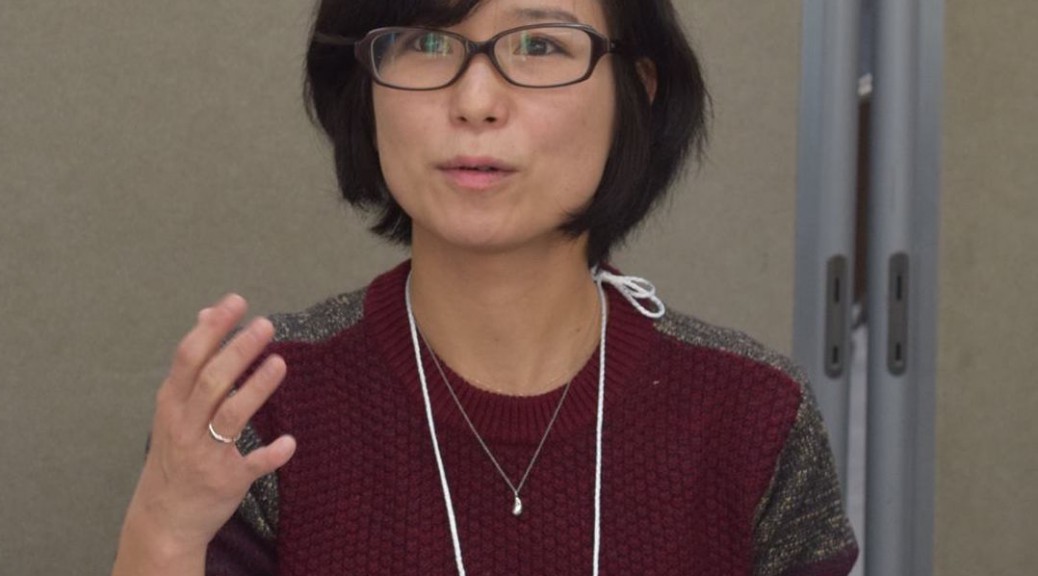ワークショップに参加した動機は?
きっかけは、2015年の8月。当時のCOJ理事の小田川華子さんと名刺交換し、COJからメールをいただくようになりました。2016年1月のワークショップの存在は知っていましたが、その日は仕事で参加できませんでした。実行委員会のメンバーから、8月のプレにお誘いをしてくださったので参加しました。でも、内容が難しくてついていけず、結局わからないまま帰ってきてしまいました。リベンジの気持ちもあり、今回の参加を決めました。
宇治でも、少子高齢化はどんどんと進み、担い手の高齢化も進んでいます。その中で、組織化された団体の支援を行うだけでいいのかという疑問と、その組織化された団体の悩みにも、具体的な解決が見いだせていないこともあり、わたしだけでなく、ほかの職員も悩んでいるところです。そして、事務分掌という枠組みだけに縛られていて、本当に地域福祉を推進することとはなにかに悩んでいました。実際に、職員を育てていくことも役割になりつつあるわたしですが、どうやっていったらいいのかも、まったくわからないままで、自分自身が不安でいっぱいでした。このワークショップを経て、自分の悩み、職員の悩み、地域福祉の課題解決に向けたエネルギーの充実など、そんな一助になればと思って参加しました。8月のプレ以降、微力ながら、実行委員で活動していることもあり、少しでも皆さんの用語についていけるようになりたいと思っていたことも、もちろんあります。
ワークショップに参加した感想は?
2日間、最初は「長いな」と思ったのですが、終わってみると体感では短かったように思います。ただ、体は正直で、すごく頭を使ったことを実証するかのような、帰りの電車では睡魔と空腹でした。同じグループで考え、学んだことを即生かすワークを行い、発表をする。その繰り返しで、次から次へと考え、ワーク、と続くため、1日目はついていくのがやっとでした。特に、1日目の「ストーリー・オブ・セルフ」は、人の前で自分の価値観を出すという、かなりの難題だったように思います。そして、なぜ、自分はそこに考えの力点を置いているのか。改めて問い直す作業でもありました。正直なところ、自分の価値観はつかみきれないまま、1日目が終わってしまい、肝心なところを落としてしまったのではないか、という感覚もありました。そのことも、コーチにフォローしてもらい、2日間を過ごすことができました。
今まで仕事の中で、地域福祉活動者の価値観に触れる場面は、何度かありました。その中で、価値観に触れたことで満足をしていましたが、それが次に結びついていないことを、今回のワークショップで感じました。それは、偶然に拾ってきた相手の価値観であること、戦略をもって聞いていたわけではなかったことなどが原因だと思います。特に、社協では、「地域組織化」を古くから進めてきていますが、「組織化」がゴールではなく、その先の「社会を変えていくこと」を見据えていたのかを確認する機会にもなりました。
また、理論を頭で考えて整理するのではなく、理論を体で覚えていく感覚が、一番新鮮でした。どうしても、研修参加になると、理論は理論で学び、ワークはワークで学びと、切り離されている感覚がありましたが、今回は流れがあり、完結していることで、より深く学ぶことができました。そして、社協職員以外の参加もあり、出会いという面ではもちろんですが、同志が社協職員以外にもいるということで、勇気づけられました。
今まで参加してきたワークショップとの違いは何ですか?
たくさん違いを感じました。まずは、コーチがグループに一人いること。それも、2日間固定されたコーチなので、このコーチと一緒に進められる安心感がありました。「自転車に乗るような感覚で」というのは、こけてもフォローしてくれる存在がいるからこそ、だと思います。時間を大切にしていること。一般の研修では、グループワークの中で時間が足りなくなると、「もう少し伸ばそうか」というようなことも見受けられますが、それは一切ありませんでした。実際に、私のグループでは、ノームコレクションもしましたし、体感で「時間の大切さ」も味わったと言えます。限られた時間の中で考えるという、徹底したその意識を感じました。
当日のタイムキーパーや環境整備をしてくださった「ロジ」の皆さんがいることで、ワークショップに集中できました。これも他にはない特徴だと思います。これらの条件があるからこそ、グループとしてのまとまり、ともに成長する感覚も生まれてくるのだと思います。
コミュニティ・オーガナイジングを今後の活動にどう活かしたいですか?
宇治市社協の取組みの中で、生かせそうなところはたくさんあります。自分が直接的にかかわっていることとして、宇治市内の別組織と合同でプロジェクトを立ち上げて、職員全員でかかわっているものがあります。その中で、具体的に、セルフ、アス、ナウを使っていけるのではないかと思っています。実際に、ワークショップで使われていた図表をもとに、プロジェクトの状況の把握を行ったりしてみたところ、現状がわかってきて、どこに力点を置いて展開を考えればいいのかも、見えてきました。
また、コーチングの部分では、どこに課題があるのかを観て、診断、介入、共有、振り返り、フォローと、まさに「自転車に乗るように」を意識することを学びました。これは職員へのアプローチとして取り入れていきたいと考えています。
実行委員としては、春ごろのあつまりで、皆さんとコミュニティ・オーガナイジングを生かした実践を共有していけたらと思います。多くの参加者が、「生かしたい」と思った気持ちが芽生えたと思うので、同志のチャレンジを、同志で共有していくことが必要かと思います。今回学んだことは即実践できることもあると思います。しかし、一緒に参加した職員も言っていましたが、コミュニティ・オーガナイジングは日本の文化の中からはぐくまれているものではないので、今いる自分の組織に、現場に、地域に、そのままあてはめるのではなく、アレンジが必要ではないかと思います。社協職員がどうアレンジをして現場で活用をしていくのかも共有しながら、社協とコミュニティ・オーガナイジングを結び付けていけたらと思います。