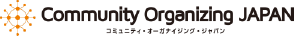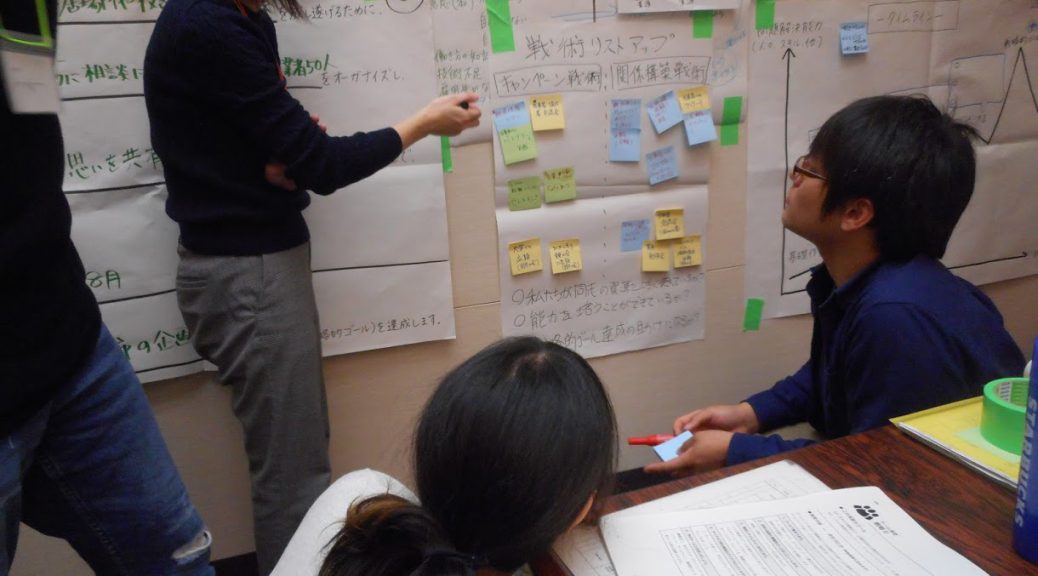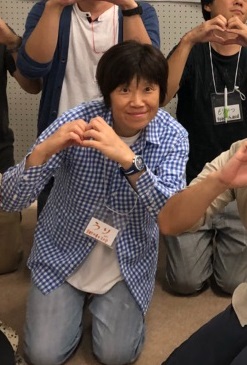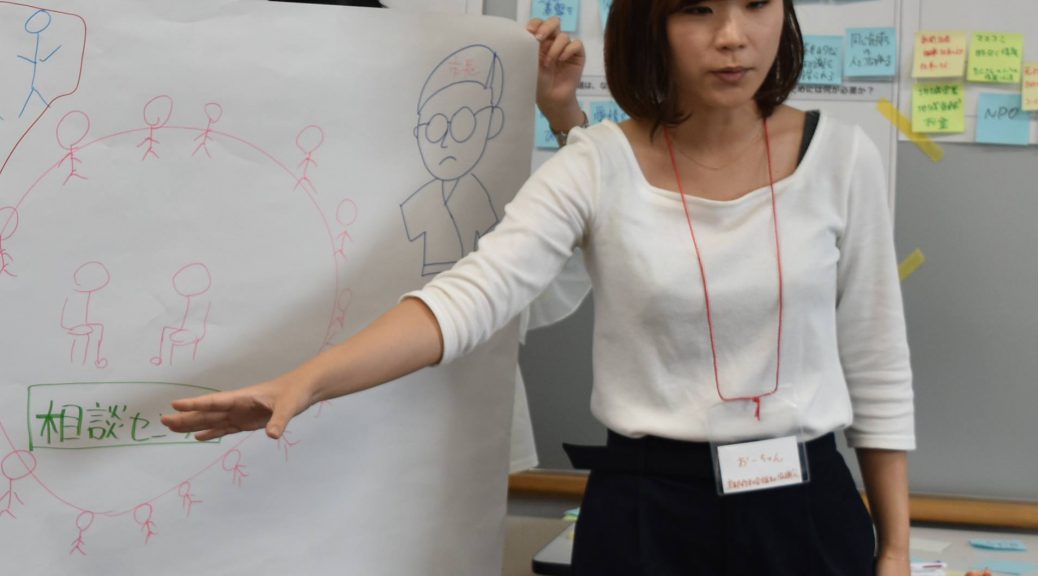ワークショップに参加した動機は?
数年前に当時の仕事を通して、コニュニティー・オーガナイジング・ジャパンについて知る機会があり、「どんなことをやっているんだろう?」と、ホームページを拝見させていただきました。【市民の力で、社会は変わる。】という言葉が目に飛び込んだ瞬間、「これは、今の私に必要なことだ!」と直感しました。ただ、それと同時に「参加したとしてついていけるのか」という不安も感じ、「参加したい!でも…」を何度か繰り返していましたが、今回、福島県内でのワークショップ(以下WS)開催とあり、また、地域や社会の課題に取り組む方々を下支えする活動を行うために勉強中の私にとって、「この機会を逃したら絶対に後悔する」と強く思ったので、不安でしたが勇気を振り絞って参加させていただきました。
ワークショップに参加した感想は?
当日の朝、凄く緊張した状態でしたが、自己紹介の際、同じように不安や緊張を感じている方がいらっしゃると知り、少し気持ちが和らぎました。そこから、本格的なワークに入っていきましたが、限られた時間の中で最大限に頭と心を回転させることの連続で、いつの間にか緊張や不安は吹っ飛んでしまいました。私にとって怒涛の二日間でしたが、チームのみんなに助けられ、支え合いながら乗り切ることができました。ある参加者の方が、ふりかえりの時間、私の発言から気づきを得たと話してくださいました。それを聞いて「こんな私でも、誰かの役に立つことができる」と感じると同時に、その方から頑張る力と勇気をいただきました。それは『誰もが誰かの力になれる』ということを、言葉ではなく、身をもって感じた瞬間でした。今後の活動で迷った時、弱気になった時、思い出して自分を鼓舞できる学びを得られたWS。参加できて本当によかったです。
今まで参加してきたワークショップとの違いは何ですか?
必ず時間を守ることです。休憩や教室移動の際に、着席や集合のカウントダウンがあり、二日間、誰一人遅れることがありませんでした。ここまで時間厳守を徹底したWSには参加したことがありませんでした。『時間は有限』ということを社会人になって改めて知らしめられ、身が引き締まりました。また、講義とワークの繰り返しでは、学んだことを直ぐに試せて、自分に足りないこと・必要なことを即座に知れ、補うには何が必要かを考え更に試すことができたので、より学びを深められるWSだと思いました。終了後、もっと学びたいと思う気持ちの方が強かったのですが、そう思えたWSも他にはないと思いました。
コミュニティ・オーガナイジングを今後の活動にどう活かしたいですか?
私は自分の考えを言葉で相手に伝えることが、あまり得意ではありません。社会や地域の課題だと感じていることがあり、その解決に「自分がどう役立ちたいか、何故それが必要なのか」を伝えることができなくて、自分が考えていることは必要なことではないのかもしれないと思い悩むこともありました。今回学ばせていただいたコミュニティ・オーガナイジングで「共感を得ること、想いを共有すること」を、実践を通して体感させていただきました。「心だけ」「技だけ」ではなく、私が実現したいことを目指すために、「心と技」を両輪として、心を込めて言葉に想いを乗せて伝え続けようと思います。そしてこれからも、コミュニティ・オーガナイジングを学び続けたいと思います。