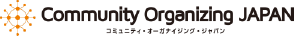今回は特別編としてグリーンズの高橋さんに今までの「グリーンズの学校」コミュニティ・オーガナイジング クラスの1〜4期を振り返って頂きつつ、参加者としてのコメントも頂戴しました。
ワークショップに参加した動機は?
「コミュニティ・オーガナイジング」クラスが、グリーンズで始まった経緯としては、グリーンススタッフの植原が、COJ主催の講座を個人的に受けていたことがきっかけでした。「ぜひグリーンズの読者にも体感してほしい!」ということで、これまで4期/45名程の方に受講頂いています。
ここから少し個人的な思いも入りつつですが。私の所属するNPOは「ほしい未来は、つくろう」をスローガンに、日本や世界の様々な「ソーシャル・デザイン」の事例をウェブマガジン「greenz.jp」で紹介し、実践者や読者と共に未来をつくっていくことをミッションとしています。そんな思いをもとに、6年前から教育事業「グリーンズの学校(旧green school tokyo)」(http://school.greenz.jp)をスタート。2年前から私は事務局としてジョインしました。
「グリーンズの学校」では、「自分もプロジェクトを始めたい」「暮らしや仕事を見つめ直したい」そんな思いを持った読者や、「共にほしい未来を一緒につくっていく仲間が欲しい」と考える取材先とが一緒に学び合うコミュニティづくりを目指しています。とはいえ私自身が日々のクラス運営に目を向けているばかりで(大事なことなんですけどね笑)コミュニティをつくることや、その先にどんな世界観をつくっていきたいかが、チームメンバーやスクール事業に関わってくれる講師やコーディネーターにもうまく伝えきれていない課題感があり、私自身も受講してみることにしました。
ワークショップに参加した感想は?
動機の部分でも少し触れましたが、私自身も「グリーンズの学校」事業を進める上で、ずっと壁にぶち当たっていました。実体の見えない「誰かのため/誰かの役に立つこと」を想定しすぎて、自分のこれまでの体験やその体験を受けてこれからつくっていきたい未来の学び・学びのコミュニティのあり方、ビジョンがまったくなかったのです。(これは今もすごい四苦八苦してます笑)
ワークショップは鎌田さんと笠井さんに「今年一番目から鱗が落ちた!」と思わず伝えてしまうぐらい、私の中で一つ壁が剥がれ落ちた感覚がありました。
普段も学びの場では「自分を主語に語ろう」というニュアンスのことは意識してますが、さらに深く、自分のストーリーを話すことになるとは。。!他の受講生も私も(一部)四苦八苦していたのを覚えています。でも、まず第一に自分のストーリーを伝えることで、相手が共感してくれる。一緒にできることを考えていくのはまず、伝えることがスタートなんだということを実感しました。
そしてついつい大きな目標を最初に設定しがちですが、戦略はもう少し素朴(身の丈感)から始めていけることも発見でした。そしてなにより、みなさんからのフィードバックが的確かつ温かみがあり、安心して場にのぞむことができました。
今まで参加してきたワークショップとの違いは何ですか?
どんなワークショップにも型であったり、メソッドはあると思いますが、それがCOの場合はとても明確に提示されていることが魅力的だと思います。テキストがホントにすごいなあと。。参考になることばかりです。あとは「コーチング」によって、参加者同士の関係が濃密になったのも印象的でした。
コミュニティ・オーガナイジングを今後の活動にどう活かしたいですか?
私自身は、繰り返し繰り返し、グリーンズで学びの場づくりを磨いていきたいと思っています。そして「グリーンズの学校」でのクラスに参加した方々の中で、自主的な勉強会グループも立ち上がりました。隔月ぐらいで活動が続いていきそうです。「復習してようやく理解できた」という学びの振り返りにもなったり「自分のプロジェクトのプロセスを、伝え合える・コーチングし合える仲間がいる」心強さがあります。次回5期も、説明会を経て2017年10月に開催を予定しているので、また新たな仲間に会えるのが今から楽しみです。
開催レポート
社会を変えたいけど、自分ひとりの力に限界を感じる。私が「コミュニティ・オーガナイジング」で学んだのは、仲間の共感を生み出す話し方
http://greenz.jp/2017/02/12/comunity_organizing_report/
これまでの開催日時
第1期
第1回 6/28 (火) 19:15 ~ 21:45
第2回 7/5 (火) 19:15 ~ 21:45
第3回 7/19 (火) 19:15 ~ 21:45
第4回 8/2 (火) 19:15 ~ 21:45
第5回 8/9 (火) 19:15 ~ 21:45
第6回 8/23 (火) 19:15 ~ 21:45
第2期
第1回 1/11(水) 19:30〜22:00
第2回 1/25(水) 19:30〜22:00
第3回 2/8 (水) 19:30〜22:00
第4回 2/22(水) 19:30〜22:00
第5回 3/8 (水) 19:30〜22:00
第6回 3/22(水) 19:30〜22:00
第3期
第1回 4/12(水) 19:30 〜 22:00
第2回 4/19(水) 19:30 〜 22:00
第3回 4/26(水) 19:30 〜 22:00
第4回 5/10(水) 19:30 〜 22:00
第5回 5/17(水) 19:30 〜 22:00
第6回 5/24(水) 19:30 〜 22:00
第4期
第1回 7/5(水) 19:30 〜 22:00
第2回 7/12(水) 19:30 〜 22:00
第3回 7/19(水) 19:30 〜 22:00
第4回 8/2(水) 19:30 〜 22:00
第5回 8/23(水) 19:30 〜 22:00
第6回 9/6(水) 19:30 〜 22:00
第5期*今週告知スタートします
第1回 11/ 6(月) 19:30 〜 22:00
第2回 11/13(月) 19:30 〜 22:00
第3回 11/20(月) 19:30 〜 22:00
第4回 12/4(月) 19:30 〜 22:00
第5回 12/11(月) 19:30 〜 22:00
第6回 12/18(月) 19:30 〜 22:00